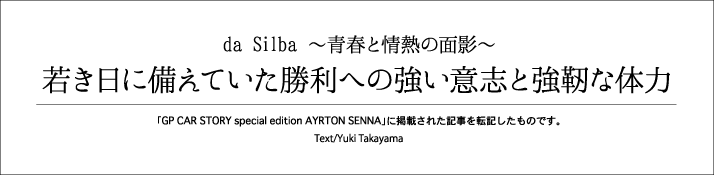
体力があったセナ
若いのに老練なレース運びをするセナだったが、それを可能としていたのが驚異的な体力による優れたタイヤマネージメント能力であったと菅家は語る。
「走りは荒いんだけど、止めるところはきちんと止める。特にタイヤが新品の時は僕らとタイム的にそんなに差がなかった。僕も世界選手権ではいいタイムを出していた方だったけど、タイヤが劣化してきた時に彼との差を感じましたね。タイヤが新品の時と古くなった時のタイヤのシャシーセットができている。僕らは常にタイヤが新しい時のセットなんですよ。だから劣化するとアンダーステアが強くなってきてタイムが徐々に落ち始める。
何でそうなるかというと、圧倒的に体力の差があるから。正直セナほどの体力を持つ日本人は、あの当時いなかったと思います。僕もモトクロス出身ですからカートでは体力がある方だった。とはいえ当時は35歳でしたからね。セナは朝一番から日がくれるまで一日中乗っていました。それなのにセッテイングを変えるとタイムが変わるんですよ。セナに『こういうふうにすればいいよ』と言われても、僕の場合良くなったっているのは分かるけど、タイムは変わらないんです」
F1ではどちらかというと体力が不安視されていたセナだったが、当時は体型もガッチリした印象を受け、驚くほど圧倒的な体力差を感じていた菅家。とにかく勝つことに執着し、カートに乗り続けていたという。
「僕との差は勝とうとする意欲と体力の差だった。体力の差によって、セッティング能力の差が出てくる。僕らは新品のタイヤでタイムを出して何とか予選を通ればいいと。決勝でどこまで行けるか。しかし彼は違いました。タイヤが劣化してきた時にどれだけタイムを落とさないように走るか。古いタイヤでもテストしますしね。それ以上テストすることないんじゃないの、と聞くと、『まだあそこはもう少し詰まる』と言うんです。日本人は誰ひとりとしてあんなに乗れなかったですよ
それにあれだけ勝利への意志が強いドライバーはなかなかいません。とにかく妥協しない。何を求めているのかと聞くと『もっと詰めるところがあるんだ。あそこであいつに離されたから、今度来たらついて行くんだよ』と言って、セッティング変えて再び走り出すんです。勝つための努力を惜しまなかった」
義理を大事にしていた
勝利に対する妥協しない姿勢は、我々がF1で見ていたセナの姿と全く同じであった。セナは誰よりもカートに乗り、自らのドライビングテクニックを研ぎ澄ませることで、抜きん出た速さを身につけていたのである。
そして、自分ひとりの力では勝てないことも彼は分かっていた。
「メカニックに言われたことはきちんと守っていましたね。もちろん朝一番から一日中乗っていますから、メカニックたちも彼を勝たせたいと思うわけです。周りの人間を動かしていたイメージが強かったです。常に誰かとしゃべっているんですよ。一度マシンから下りたら車の中に閉じこもってしまうドライバーもいますが、彼にはそういうことがない。常にマシンの側にいて、『こうしよう、ああしよう。あそこはこうして、こうなるんじゃないか』ってそうするとメカニックも納得してセナの言うとおりになる。だからセッティング能力がズバ抜けていましたね」
また、彼なりの心遣いもあったという。
「派手に誰かを怒ったりはしなかったですね。いつもニコニコしていました。メカニックとのやりとりで興奮気味に話すことはあっても、それに対してメカニックは嫌な感情は持っていなかった。お互い良い関係を築いていたと思います」
20歳前後のブラジルの若者が、単身ヨーロッパに乗り込みレースの本場で成功するのは容易なことではない。だからこそセナは、周囲の強力なサポートを必要とし、彼らとの関係を大事にしていた。特に自分のヨーロッパでのレース活動をサポートしてくれた、DAPの社長アンジェロ・パリラには特別な恩義を感じていた。菅家が回想する。
「一度セナになぜカートを続けるのか聞いたことがありました。そうしたら『DAPで世界チャンピオンを獲ってアンジェロに恩返ししたいんだ。F1で世界王者になるつもりでいるけど、その前にカートで世界王者になって恩返ししてからF1に行きたい』と言うんです」
セナはその時すでにフォーミュラカテゴリーへステップアップしていたが、カートレースへの出場は続けていた。
「年に一回だけど世界選手権には挑戦するんだ」―。
結局セナはカートで世界を制することはできなかった。しかし、その義理堅い気持ちは希望に満ちた日々の中で芽生えた彼なりの優しさだったのかもしれない。
そんな日本人も大事にする感情を若き日に抱いていたセナだったが、菅家は当時セナと日本についても話をしたことがあったという。
「基本的に日本のことが好きでしたよ。やはりタイヤ関連の話が中心ではありましたが、僕のこともすごい大事にしてくれましたしね。タイヤについては『こういうふうにしたらどうなんだ』とかいろいろ聞いてきました。日本製のものを信頼していましたよね。ただ、日本でなぜフレームメーカーやエンジンメーカーができないのか不思議がっていた。四輪にしても二輪にしても当時からすごかったじゃないですか。『レース文化があるのはホンダだけだね』って。日本のそういうのに興味があるわけですよね。ホンダはすでにF1で優勝していたし、『いつかホンダのマシンに乗ってみたい』とも言っていました」
意外だったセナの最期
82年を最期にカートを完全に卒業したセナは、83年にイギリスF3、マカオF3を制し、84年にトールマンからF1デビューを果たす。特にトールマン時代の84年、ロータス時代の85年、86年、そして非力なフォード・エンジンで臨んだマクラーレン時代の93年のセナは、カート時代と同様に劣勢の中で臨まなければならない環境だった。そんなセナの姿を菅家がどう見ていたのか。
「彼のドライビングテクニックの基礎はカートから来ていたし、決して満足できない体制の中で活躍していた経験が活きているなと思いました。すぐにチャンピオンを獲ると思っていましたよ。ロータス・ホンダに乗れた時もうれしかったですね。ああ、ようやく乗れたんだって」
そして94年、運命のサンマリノGP。当時テレビで観戦していた菅家は、事故の瞬間を見てすぐに不幸な結末を感じたという。
「左に曲がるコーナーで右に真っ直ぐ行きましたから。ステアリングのどこかがトラブルを起こしたんだろうなと思いました。仮にオーバースピードだったとして、普通だったらハンドルを切りますが、そういう感じではなかった。真っ直ぐ行ったのでステアリング系だと思いました」
ただ菅家にとって、あのような最期は想像できなかった。
「セナだけは死なないと思っていました。彼は突っ込む時は自分で100%理解して突っ込んでいる。行けるか行けないかでは入らない。自分では行けるっている100%の確信で入っていく。だからカートでは絡まなかった」
結局、カート時代以降はセナと再会することはなかったが、交友関係は続いていた。
「実は94年の日本GPに招待されていたんですよ。僕も楽しみにしていたんですが、結局あんなことになってしまって……。それと、セナは亡くなるまで毎年クリスマスカードを送ってきてくれたんです。一度F1ドライバーになってから時計をもらったこともあります。ホンダF1の刻印がされているものでした。とても義理堅い人間ですよね。日本人に近いというか。ああいう人間はなかなかいませんよ」
セナは生前「レースにかける僕の献身、愛情はカート時代に培われた。カート時代が自分にとって最も幸せなレーシングライフだった」と語っている。そんな時を過ごしていた彼と出会い、チームメイトとして同じ時間を共有した菅家にとっても、同じように幸せな日々だった。
セナが日本を愛したように、日本もセナを愛した。その関係性を紡いだひとつの出会いが、その時代にあったのだ。(文中敬称略)
Copyright© 2009 うるし紙 菅家 All Rights Reserved.